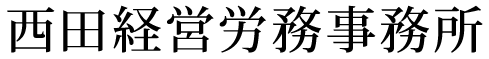その病歴・就労状況等申立書 墓穴を掘っていませんか
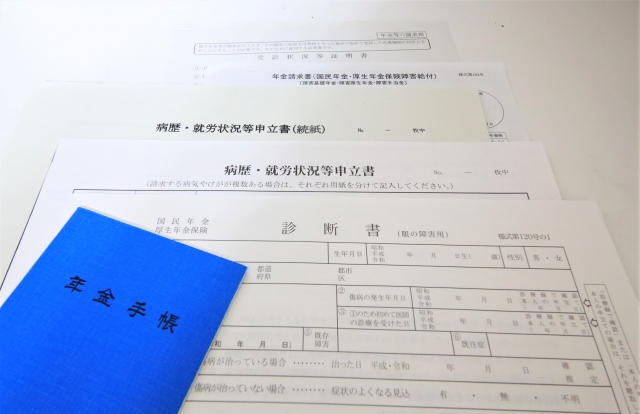
その原因の多くは、病歴・就労状況等申立書の内容に関することが多いのが現状です。
病歴・就労状況等申立書は、障害年金の審査において、診断書や受診状況等証明書を補完する非常に重要な書類です。
この申立書は請求人本人、あるいは請求人の家族などが記載する書類です。
ある意味では、請求人本人やその家族などの判断や意思で自由に記載できます。
しかし、あまりにも独りよがりな、自己満足的な要素が濃厚であれば、思わぬ墓穴を掘ることになりかねません。
つまり、記載欄いっぱいにただ書けばよいというものではない、ということです。
請求人自身の言葉で病歴や日常生活、就労の状況を伝えるため、この書類の作成が不適切だと、本来受給できたはずの年金が不支給になったり、低い等級で認定されてしまうという「残念なケース」が発生します。
ここでは、その代表的な残念なケースと、避けるべきポイントを解説します。
目次
症状や日常生活の状況が過小評価・過大評価されるケース

☆過小評価(頑張りすぎた記述)
これは、症状や日常生活、就労状況の困難さを軽く書いてしまう、または「調子の良い時」の状態のみを強調してしまうケースです。
例
・うつ病でほとんど家から出られない状態なのに、「散歩はできます」とだけ記載し、散歩後の強い疲労や抑うつ状態を追記しない。
その結果、審査官が書類を読むと「この人は日常生活が比較的できている」と判断し、障害の程度が軽く評価され、不支給や低い等級(3級など)となる。
対策
・「日常的な困難さ」と「最悪の状態」を具体的に追記する。
・介助や援助を受けている事実(家族や支援者に頼っていること)を省略しない。
☆過大評価(症状と診断書が一致しない)
これは、申立書に記載された症状の程度が、医師が作成した診断書の記載内容と著しく乖離しているケースです。
例
・申立書では「全く動けない」と書いているのに、診断書の「日常生活能力の判定」では高い点数になっている。
その結果、申立書の信ぴょう性が疑われ、「申立書に記載された障害の程度は事実ではない」と判断されるリスクが高くなる。審査官は診断書を最も重要な証拠とするため、申立書のみを根拠に等級を上げることは難しくなってしまう。
対策
・医師と面談し、診断書の内容を確認したうえで、申立書を作成する。
・診断書で伝わりにくい「具体的なエピソード」を補完する形で記述する。
病歴・受診状況に関する記述漏れや矛盾

☆受診状況の記述漏れ(初診日が揺らぐ)
請求している病気に関する過去の受診や、症状が出始めたころの軽い受診歴を「たいしたことない」と自己判断し、申立書への記載を省略するケースです。
例
・胃がんで請求する際、その10年前に胃の不調で一度受診した事実を記載しない。
結果
・審査機関が医療記録を照会した際、記載のない受診歴が発見されると、申立書に記載した「初診日」が否定され、初診日の証明書類(受診状況等証明書)の再取得が必要になるなど、手続きが大幅に遅延したり、最悪の場合、納付要件を満たせず不支給となる。
対策
・「悪化期」「回復期」「安定期」など、時期を区切って、その期間の症状や生活状況を具体的に説明する。
就労状況に関する記述の誤解

☆就労の「実態」を反映できていない
これは、現在も働いている事実がある場合、「時短勤務」「配置転換」「家族や同僚の援助」など、「障害によって配慮を受けている実態」を具体的に記載しないケースです。
例
・「一般企業で働いている」とだけ記載し、実際には仕事の半分以上を同僚に手伝ってもらっている事実を記載しない。
結果
・審査官は「一般の労働能力がある」と判断し、等級の認定に非常に不利となる。特に精神障害においては、就労の実態(配慮の有無)が等級認定の重要な判断材料となる。
対策
・「職場で受けている特別な配慮」を具体的にリスト化する。
・仕事が「できたこと」ではなく、「できなくなったこと、または援助がなければできないこと」を中心に記述する。
心情やプライベートな出来事を書いても…

また、よくある例ですが、自身の経済的に困窮している状況や心情、親や子どもなど援助している方のプライベートな出来事を延々と病歴・就労状況等申立書に記載する方がいます。
請求人自身の、申請する障害に至った傷病の治療とは全く関係のない話であることは
言うまでもありません。
このように、障害に至った本人の傷病と全く関係の無い事柄を詳しく記載しても、全くメリットはなく、むしろ申立書のアピール度が薄まってしまい、主要ポイントがどこにあるのか全く分からなくなってしまいます。
つまり、この病歴・就労状況等申立書を読むであろう審査担当者の頭の中に、請求人自身の病状や、いかに仕事や日常生活で困難を抱えているか、その情景が浮かび上がってくるような表現内容でなければ、意味のないものとなってしまうのです。
まとめ

病歴・就労状況等申立書は、診断書を補完し、請求人の「生の声」を伝える唯一の機会です。
これらの残念なケースを避け、ご自身の障害の状況や日常生活上の困難さを正確に伝えるためには、専門家である社会保険労務士のサポートを受けることも有効な手段となります。
シェアする