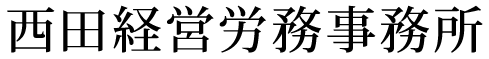知的障害での障害年金 早い段階から申請準備を ~20歳からの受給を見据え、今から知っておくべきこと~

障害認定を受ければ、20歳になったら「20歳前の障害基礎年金」を受給することができます。
特に「親亡き後」、残された子どもはどうなるのだろうと、将来についての悩みや不安をお持ちの方は多いと思います。
障害年金は、お子さんが将来にわたって安定した生活を送るための大切な支えとなる可能性があります。
障害年金が申請できるのは20歳になってからですが、今回は、障害年金がどのような制度で、知的障害の場合どのように適用されるのか、そして申請に向けて何から始めれば良いのかを、わかりやすく解説します。
目次
障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障がある場合に支給される公的年金制度です。大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
発達障害のお子さんの場合、20歳前に診察があれば「20歳前障害」と判断され、基本的には「障害基礎年金」となる場合が多いです。
ここでは、主に障害基礎年金の仕組みと受給要件を簡単に説明します。
①障害基礎年金の仕組み
障害基礎年金は、公的年金の1階部分にあたる「国民年金」に加入している人が対象となる年金です。自営業者、専業主婦(夫)、学生など、国民年金のみに加入している方が主な対象となります。
障害の程度に応じて、1級と2級の2段階が設けられており、障害の程度が重いほど支給額も高くなります。
令和7年度受給額
・1級 年額1,039625円
・2級 年額831,700円
②障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1)初診日要件
障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(「初診日」といいます)が、以下のいずれかの期間にあること。
1.国民年金に加入している期間
2.20歳前
3.日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合を除く)
ポイント: 初診日がいつか、証明できる資料(診察券、領収書、カルテなど)があることが非常に重要です。初診日が特定できない場合、申請が難しくなることがあります。
※知的障害や発達障害などの場合、療育手帳があれば、「初診日」は「出生日」となり証明資料として使用できます。
2)保険料納付要件
初診日の前日において、以下のいずれかの条件を満たしていること。
1.原則: 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納付した期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること。
2.特例: 初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(この特例は、2026年3月31日までの時限措置です)
ポイント: 国民年金は自分で保険料を納める必要があるため、未納期間があると受給できない場合があります。厚生年金に加入している会社員や公務員は、給与から天引きされているため、原則として未納は発生しません。
20歳前傷病の場合: 20歳前に初診日がある場合は、年金制度に加入していないため、保険料納付要件は不要です。
3)障害の状態要件(障害等級)
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日、または症状が固定した日など)において、障害の状態が「障害等級表」に定める1級または2級に該当していること。
①1級: 他人の介助がなければ日常生活がほとんどできないほどの状態。
②2級: 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態。
ポイント: 障害者手帳の有無は障害年金の受給とは直接関係ありません。障害年金の等級は独自の基準で判断されます。また、障害認定日に該当しなくても、その後症状が悪化して障害等級に該当した場合は「事後重症」として請求することもできます(65歳誕生日の前々日まで)。
※障害厚生年金は3級までありますが、障害基礎年金は2級までです。
障害年金を受給するメリット

障害年金を受給するメリットは多岐にわたりますが、大きく分けて経済的なメリットと精神的なメリットがあります。
①経済的なメリット
1.安定した収入の確保
病気やケガによって仕事ができない、または制限される場合、収入が大幅に減少することがあります。障害年金は、障害の程度に応じて定期的に支給されるため、生活費や治療費の心配を軽減し、経済的な安定をもたらします。
2.非課税であること
障害年金は所得税や住民税などの課税対象になりません。そのため、受け取った金額をそのまま生活費などに充てることができ、実質的な手取り額が多くなります。老齢年金など他の公的年金は課税対象となる場合があるため、この点は大きなメリットです。
3.国民年金保険料の法定免除
障害基礎年金の1級または2級を受給している場合、国民年金保険料の支払いが法定免除となります。これにより、保険料の負担がなくなるだけでなく、免除された期間は将来の老齢基礎年金の受給額にも一部(半額分)反映されます。
4.就労していても受給できる場合がある
障害年金は、必ずしも働けないことを前提としているわけではありません。障害の状態によっては、働きながらでも受給できる場合があります。これにより、給与収入と合わせてより安定した生活を送ることができます。
5.使い道が自由である
障害年金として受け取ったお金の使い道には制限がありません。生活費、治療費、リハビリ費用、さらには貯蓄やローン返済など、ご自身の状況に合わせて自由に使うことができます。生活保護など、他の公的支援制度では使い道に制限がある場合もありますが、障害年金は自由度が高いのが特徴です。
6.将来の老齢年金が減額されない
障害年金を受給したからといって、将来受け取る老齢年金が減額されることはありません(ただし、上記の法定免除を利用した場合、その期間の老齢基礎年金は一部減額されますが、任意で保険料を納めることも可能です。)
②精神的なメリット
1.経済的な不安やストレスの軽減
収入が不安定になったり、治療費がかさんだりする経済的な不安は、病状の悪化や精神的な負担につながることがあります。障害年金の受給により、経済的な基盤が安定することで、金銭的な不安やストレスが軽減され、安心して治療やリハビリに専念できる環境が整います。
2.自己肯定感の向上
障害によって仕事や社会参加が難しくなった場合、自己肯定感が低下することがあります。障害年金を受給し、経済的な自立を支援されることで、精神的なゆとりが生まれ、自己肯定感の向上や社会とのつながりを保つことにもつながります。
3.治療への専念
経済的な心配が減ることで、焦って無理に働いたりせず、治療や休養に集中できる時間が増えます。これは、病状の回復にとって非常に重要です。
4.周囲に知られにくい
原則として、障害年金を受給していることが職場や親族など、周囲に知られることはありません。プライバシーが守られるため、安心して制度を利用できます。
これらのメリットは、障害を持つ方がより安定した生活を送り、病状の回復や社会参加に向けて前向きに取り組むための大きな支えとなります。
知的障害の認定基準

障害年金を申請するにあたり、厚生労働省では「障害年金の認定基準」が設けられています。
それによると、「知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう」とされています。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
1級:知的障害があり、食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級:知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
具体的にどのような点が評価されるか、以下にまとめます。
1. 日常生活能力の評価
診断書には、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という項目があり、ここで具体的な日常生活での困難さが評価されます。
(1)日常生活能力の判定(7つの項目での評価)
以下の7つの項目について、「できる」「おおむねできるが時には助言や指導を必要とする」「助言や指導があればできる」「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の4段階で評価されます。
①適切な食事
食事の準備、バランスの取れた食事、食習慣など
②身辺の清潔保持
入浴、洗髪、着替え、自室の清掃・片付けなど
③金銭管理と買い物
金銭の管理、計画的な買い物、金銭トラブルの有無など
④通院と服薬(要・不要)
自分で通院・服薬ができるか、服薬管理ができるかなど
⑤他人との意思伝達及び対人関係
他者とのコミュニケーション、人間関係の構築・維持、集団行動の困難さなど
⑥身辺の安全保持及び危機対応
危険を察知し回避できるか、緊急時の対応など
⑦社会性
周囲の状況に合わせた行動、社会規範の理解と遵守など
これらの項目において、具体的なエピソードや支援の必要性が重要視されます。例えば、一人暮らしができていても、実は家族やヘルパーの継続的な支援があって初めて成り立っている場合などは、その支援内容を具体的に伝える必要があります。
(2)日常生活能力の程度(総合的な評価)
上記の各項目を踏まえ、日常生活全般における障害の程度を5段階で評価します。
2. 社会生活への適応状況の評価
日常生活能力の評価に加えて、就労状況や学校生活、地域での活動など、社会生活への適応状況も重要な判断材料となります。
①就労状況
就労している場合でも、仕事の種類や内容(単純作業、反復作業など)、就労時間、職場で受けているサポート内容(指示・指導、人間関係の調整など)、他の従業員との意思疎通の状況などが詳しく確認されます。
「働いているから年金はもらえない」ということはなく、配慮や援助がなければ就労が困難であるという状況が重要です。休職や離職を繰り返している場合、その経緯も重要な情報となります。
②学業・通学状況
学生時代に不適応があった場合(いじめ、不登校、転校、留年など)のエピソードも考慮されます。
③社会参加・対人関係
家族以外の者との交流の有無、趣味活動やボランティア活動への参加状況、友人関係の状況なども評価対象となります。ひきこもりの状況なども含まれます。
3. 知的障害特有の考慮事項
「知的障害の認定基準」では、知的障害に特有の考慮すべき要素も明記されています。
①知的障害の認定に当たっては、知能指数にのみ着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
②日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
③就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労している者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
「生活のしづらさ」を具体的に
「生活のしづらさ」を正確に伝えるためには、以下の点が重要です。
詳細な病歴・就労状況等申立書: これまでの生活の困難さや、仕事・学業での具体的な支障、周囲からの支援内容などを、幼少期から現在まで時系列で具体的に記述することが非常に重要です。客観的な事実(例:何度も転職した、いじめられた、ヘルパーに週〇回掃除に来てもらっている等)を記載します。
①医師との連携
主治医に自身の具体的な日常生活の困難さを正確に伝え、診断書に反映してもらうことが不可欠です。診察時にメモを持参したり、家族が同席して説明したりすることも有効です。
②客観的な視点
ご本人が「できているつもり」でも、実際には多大な努力や周囲の支援があって初めて成り立っている場合があります。客観的な視点から、何ができていて、何が難しいのか、どのような支援が必要なのかを具体的に示すことが求められます。
知的障害は、「見た目には障害が分かりにくい」方も多いため、その障害ゆえの生活上の困難さをいかに具体的に、かつ客観的に示すかがポイントとなります。
20歳前からの申請準備として、具体的な「困りごと」の例を短く箇条書きで示すことから始めてみましょう。
この時の注意点は、「親や兄弟がいるからできていること」が「1人暮らしをしてもできること」なのかという点です。
親や兄弟など助けてくれる人いるから、本人も親も不便に感じていなくても、本人1人ではできないことが多いはずです。
「1人でできるかできないか」その点を客観的に判断することが、本当の困りごとを見極めるポイントです。
知的障害による障害年金申請でよくある誤解

知的障害の方が障害年金を申請する際には、いくつか誤解しやすい点があります。これらの誤解が原因で、申請がスムーズに進まなかったり、不支給になったりするケースも少なくありません。
①「IQの数値だけで等級が決まる」という誤解
知的障害の判定にIQが用いられるため、IQが70~75といった軽度な範囲だと「障害年金は無理」だと思い込まれる方がいます。
しかし、障害年金の審査は先にも述べましたが、IQ数値だけでなく、「日常生活能力」や「社会生活への適応困難の程度」が最も重視されます。
たとえIQが軽度とされる範囲でも、一人で金銭管理ができない、交通機関の利用が難しい、対人トラブルが多いなど、日常生活や社会生活に著しい制限があれば、十分に支給対象となります。
②「働いているから対象外」という誤解
現在就労継続支援B型事業所等の福祉的就労をしている、障害者雇用枠での就労をしている、あるいは一般雇用で就労している等の場合、「働けている=自立できる」と考え、障害年金の支給対象ではないと誤解される方もいます。
しかし、重要なのは「どれくらいの支援を受けて働けているか」という点です。
一般就労であっても、頻繁に職場の人間関係や業務でトラブルがあり、短い期間で転職を繰り返している(職場の支援が常時必要な状態)場合は、障害の程度が重いと判断されます。
申請書類(特に病歴・就労状況等申立書)には、仕事や生活で具体的にどのような失敗や困難があり、誰にどのような支援を受けているかを詳しく記載する必要があります。
③「申請書類の記載内容が不十分でも実態は伝わる」という誤解
医師の診断書や本人の申立書に、生活上の困難を詳しく書かなくても、療育手帳の等級などで実態は伝わると思い込んでしまう場合があります。
障害年金の審査は、「提出された書類」のみに基づいて行われる書面調査です。
「買い物に行ける」「仕事に行っている」といった表面的な情報だけでは、「問題なく生活できている」と誤解され不支給につながってしまいます。
具体的なエピソードを交え「金銭管理ができない」「指示がないと身の回りのことができない」「災害時に1人で行動できない」「他人から騙されやすい」といった、支援なしでは生きていけない実態を診断書と申立書で一貫して示すことが非常に重要です。
④「保険料納付要件が必要」という誤解
障害年金は、原則として保険料を一定期間納めないと受給できないため、知的障害でも同じ納付要件が必要だと思い込んでしまう例があります。
知的障害(先天性の精神遅滞)の場合、障害年金の申請における初診日は、原則として出生日として取り扱われます。
20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。
したがって、知的障害は障害基礎年金の対象となります。ただし、年金が支給されるのは20歳からです。
これらの誤解を避けるためには、「日常生活における具体的な困難の程度」「就労する上で受けているサポートや必要な支援」について、医師の診断書とご本人の申立書で徹底的に詳細かつ正確に伝えることが成功のカギとなります。
障害年金への具体的ステップ

では、20歳前から障害年金の申請に向けて、どのような準備をすればよいのか具体的なステップをみていきましょう。
①情報収集
まずは、ご自身で大まかな情報を集めてみましょう。日本年金機構のウエブサイトや、障害年金に関する書籍などが参考になります。また最近では「親亡き後」をテーマにした様々なセミナーや講演会が行われています。このようなセミナーでは障害年金だけでなく、様々なサポートについて知ることもできるので、有効に活用しましょう。
②相談窓口の活用
お住いの地域の年金事務所、街角の年金相談センター、又はお近くの社会保険労務士(障害年金専門の社労士もいます)に相談してみましょう。無料で相談できる窓口もあります。
直接相談に出向くことに抵抗がある方は、NPO法人障害年金支援ネットワークの電話相談があります。全国どこからでも相談を受け付けてくれます。
③主治医との相談
障害年金の申請を考えていることを主治医に伝え、診断書作成について相談しましょう。
障害年金の申請には、医師による診断書が必須です。そして、この診断書が審査において重要な役割を占めます。
日頃からお子さんの困りごとや特性について、主治医とよくコミュニケーションを取り、具体的な情報を伝えておくことが大切です。
まとめ
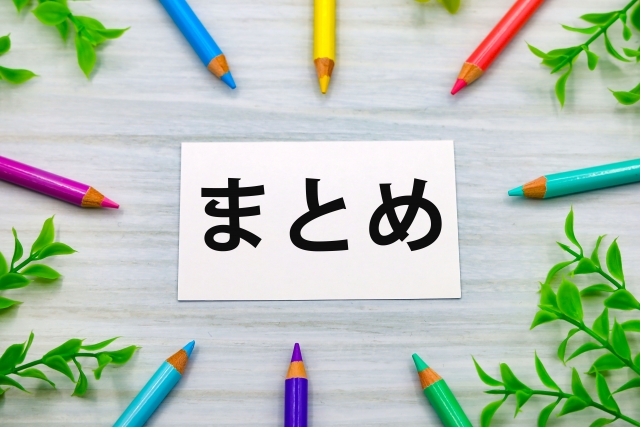
「もっと早く知っていれば」「程度が軽いので申請できるとは思わなかった」など悔やむ声も聞かれます。
当事務所においても、40代50代まで生きづらさを感じ、やっと検査を受けて軽度知的障害と判断され、障害年金の受給に至ったケースは少なくありません。
障害年金は決して難しいことばかりではありません。
正しい情報を知り、適切なサポートを得ることで道は開けます。
知ることで、お子さんの未来の選択肢が広がるかもしれません。
お子さんの将来の安心のために、一歩踏み出す勇気が必要です。
まずは、今日から情報収集を始めてみませんか。
そして、困った時は行政の相談窓口や、障害年金の専門家である社会保険労務士に
気軽に相談してください。
シェアする