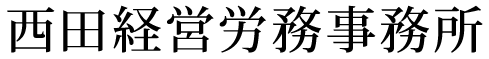障害年金が通った後の生活は?受給後の「自立した生活」を支える福祉サービス

これでようやく生活の土台ができ、一安心されたことしょう。
しかし、ほっとしたのと同時に「これからどうやって働いていけばいいんだろう」「生活リズムをどうやって作っていけばいいんだろう」と新たな不安を感じていませんか。
障害年金の受給決定はゴールではなく、新たなスタートです。
私たちの社労士事務所には、年金の手続きを行う社会保険労務士に加え、生活全般の相談援助を専門とする社会福祉士が在籍しています。
この記事では、あなたの「自立した生活」を築くために、年金とセットで利用できる、社会福祉士が提案する福祉サービスの具体的な活用方法を紹介します。
目次
「自立した生活」を支える具体的な福祉サービス

ここでは、年金を受給しながら、あなたの体調や目標に合わせて利用できる福祉サービスを紹介します。
特に、「就労」と「生活リズムの安定」に役立つサービスは、年金受給者にとって重要な柱となります。
就労を目指す方・続けたい方を支えるサービス
①就労継続支援B型(雇用契約を結ばない、作業を通じたリハビリの場)
「まだ体調に波があって、毎日決まった時間に働くのは難しい」
「まずは社会との接点を持ちたい」
このような方にお勧めしたいのが、就労継続支援B型です。
国の障害福祉サービスの一つで、働く機会と訓練を提供することが主な目的です。
🌟 重要な3つのポイント
・雇用契約がない
一般企業や就労継続支援A型と違い、作業所と雇用契約を結びません。
そのため、体調や障害に合わせて、週に数時間からなど、非常に柔軟な働き方ができます。無理なく自分のペースで通い、作業に慣れることができます。
・賃金は「工賃」として支払われる
作業の対価として「工賃」が支払われます。給料とは異なり、最低賃金の適用はありません。(そのため、一般の給与と比べると金額は低い傾向にあります。)
・作業内容
事業所によって様々ですが、軽作業(袋詰め、部品の組み立て、シール貼り)、清掃、農作業、パンやお菓子の製造、パソコン入力など、比較的簡単な作業が多いです。
これらの作業を通じて、働くための知識や能力を身につけたり、生活リズムを整えたり、社会参加の機会を得たりします。
🌟社会福祉士からの視点:年金との賢い組み合わせ方
障害年金は、働く能力が制限されていることに対する補償であり、年金を受給しながら就労継続支援B型を利用することは全く問題ありません。
B型の工賃(給料ではなく作業対価)は多くの場合、最低賃金より低く設定されていますが、年金があることで経済的な焦りから無理に高収入の仕事を探す必要がなくなります。
【活用例】
・生活リズムの確立:週3日、午前中のみB型に通い、規則正しい起床・就寝を習慣化する。
・体調の波への対応:体調が優れない日は柔軟に休むことができ、症状が悪化することを予防することができる。
・社会参加:職員や他の利用者との交流を通じて、社会的な孤立を防ぐことができる。
②就労移行支援(一般企業への就職訓練)
「体調は安定してきたので、2年以内に一般企業で働きたい!」という目標がある方には、就労移行支援が適しています。職業訓練や応募書類の作成、面接練習など、就職活動全般をサポートしてくれます。
🌟 重要な3つのポイント
・目的は「一般就職」
最終的な目標は、企業などに直接雇用されて働くことです。そのため、事業所での訓練期間は原則として最長2年間と定められています。
・訓練とサポートの内容
働くために必要な知識やスキルを身につけるための訓練を行います。(例:PCスキル、ビジネスマナー、コミュニケーション、体調管理など)
自分に合った仕事探しや、履歴書作成、面接練習などの就職活動をサポートします。
・職場定着の支援
就職した後も、職場に慣れるためのサポート(職場の人間関係の相談、業務量の調整サポートなど)を受けられます。
🌟社会福祉士からの視点:キャリア構築と目標達成のツール
就労移行支援事業所は、「就労」という明確な目標達成のための「専門的な訓練機関」として活用します。
就労に必要なスキル・知識の獲得として、企業で働くために不足しているPCスキル、ビジネスマナー、専門知識などを集中的に学ぶ場として活用し、利用者の能力開発(エンパワメント)を促進します。
そして、職場実習などを通じて、クライエントの得意・不得意な作業、ストレス要因、必要とする合理的配慮を具体的に把握します。これにより、ミスマッチのない最適な就職先を見つけるための判断材料とすることができます。
地域生活を安定させるサービス
年金受給で経済的な土台ができても、自宅での孤独感や、生活上の困りごとを抱えることがあります。
①相談支援事業所(福祉サービスの計画作成)
相談支援事業所は、「障害のある方やそのご家族が地域で安心して生活を送るために、必要な福祉サービスの情報提供や、利用計画の作成、関係機関との調整を一貫して行う相談窓口」です。
簡単に言えば、福祉サービス版の「ケアマネジャー」のような役割を担い、複雑な福祉制度の中で、利用者一人ひとりに最適な支援をコーディネートする専門機関です。
相談支援事業所が行う支援は、大きく分けて以下の3種類があります。
・基本相談支援(まずはここから)
障害のある方やご家族からの、日常生活に関するあらゆる困りごとや不安についての相談を受け付けます。「どこに相談したらいいか分からない」といった最初の窓口にもなります。
そして、福祉サービスや社会資源に関する情報提供、各種手続きの案内、必要に応じて他の専門機関へのつなぎ約を果たします。
・計画相談支援・障害児相談支援(サービス利用の必須ステップ)
障害福祉サービス(就労移行支援、放課後等デイサービス、ホームヘルプなど)を利用するために必須となる計画を作成性、その後のサービス利用を支えます。
サービスの内容は、相談支援専門員が本人やご家族と面談し、希望や課題、目標などを聞き取り、最適なサービスを組み合わせた個別支援計画を作成します。
サービス開始後も、計画通りに支援が行われているか、利用者に合っているかを定期的に確認し、必要に応じて計画の見直しや調整を行います。
・地域相談支援(地域生活を支える)
施設や病院から地域生活へ移行する方、または地域での生活を不安なく継続したい方を専門的に支援します。
例えば、入院・入所している方が地域生活へ移るための住居の確保や、福祉サービスの見学・体験などをサポートします。
さらに、地域で一人暮らしなどをしている方が、緊急時に備えて24時間連絡できる体制を確保し、トラブルや不安が生じた際に緊急訪問や関係機関との調整を行います。
🌟社会福祉士からの視点:あなたに最適なプランニングを
相談支援専門員(多くの事業所に社会福祉士の資格保有者がいます)は、あなたの生活状況、目標、医師の意見等を聞き取り、どのサービスをどのくらいの頻度で利用するのが最適かを専門的に計画します。この計画があることで、年金受給後の生活が「見える化」され、不安が和らぎます。
まとめ
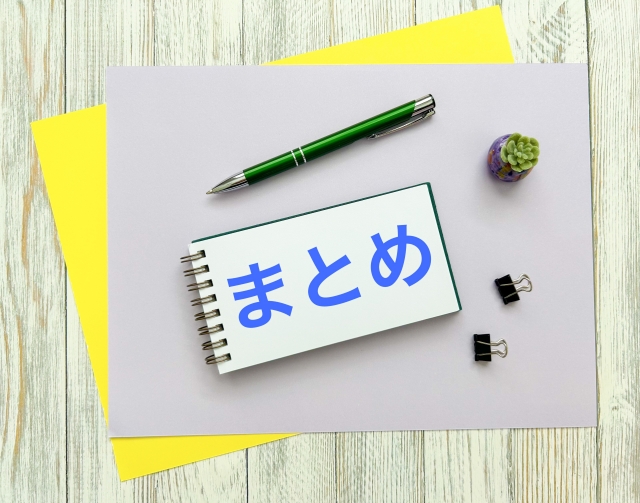
年金受給後の生活再建は、一人で抱え込む必要はありません。
まずはあなたの今の悩み、将来の希望を、生活再建の専門家である社会福祉士にお話しください。
年金受給後の生活不安、福祉サービスの利用方法について、まずはお気軽にご相談ください。
シェアする