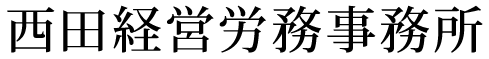障害年金の結果が届いた!まず見るべきはココ!年金決定通知書の超重要ポイント
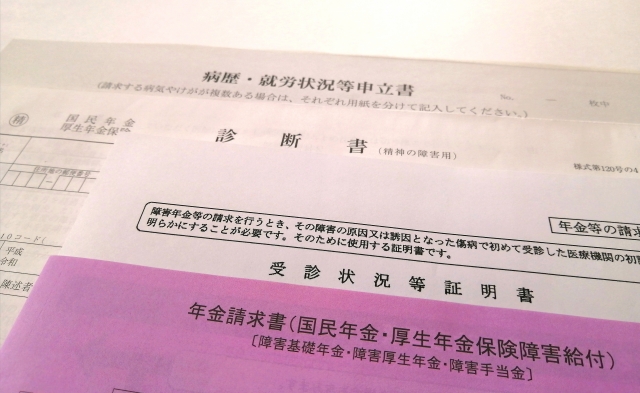
そして、結果を待つ時間は、不安と期待が入り混じり、とても長く感じられるものです。
この記事では、「障害年金の結果をどうやって知るのか」という疑問に、具体的に、そして分かりやすくお答えします。
「いつ、どこに、どんな通知が届くのか?」
「不支給になってしまったときはどうするのか?」
申請後の手続きの全体像と具体的な方法を解説していきます。
目次
- ○ 障害年金の結果はどうやって知る?
- ・年金証書(年金決定通知書)で確認すべき5つの超重要ポイント
- ○ 不支給!?却下!?どうすればいい?
- ・不支給決定通知とは
- ・却下通知とは
- ・障害等級の決定に関する情報の入手
- ・裁定請求書のコピーは保管していますか
- ○ まとめ
障害年金の結果はどうやって知る?
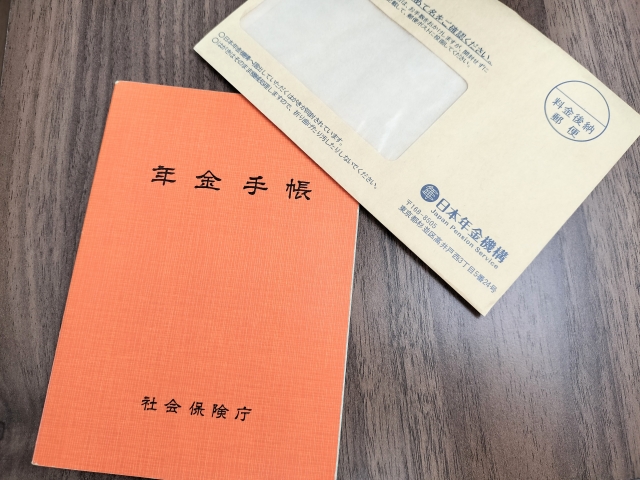
障害年金の請求書を年金機構へ提出してから、概ね3か月程度で審査結果が届きます。
年金受給が決定されれば、「年金証書(年金決定通知書と一体化)」が年金機構から自宅へ郵送されます。
障害年金を受け取れない場合には、日本年金機構から不支給決定通知書が送付されます。
これについては、後述いたします。
年金証書には、あなたの今後の生活に直結する重要な情報がぎっしり詰まっています。
この書類が届いたら、まずは以下の5つのポイントを必ず確認しましょう。
年金証書(年金決定通知書)で確認すべき5つの超重要ポイント
1. 障害等級:あなたの障害状態が何級と認定されたか?
年金決定通知書の最も重要な項目です。
あなたの障害状態が「1級」「2級」「3級」のどれに認定されたかが明記されています。
この等級によって、受け取れる年金額が大きく変わります。
2. 支給開始年月:いつから年金がもらえるのか?
年金は申請した月の翌月以降に支給されます。
この「支給開始年月」は、いつから年金の支給が始まるのかを示すものです。
ここに記載された月から、実際に年金が振り込まれることになります。
特に、遡って支給される「遡及請求」が認められた場合、この日付が数年前になることもあります。
3. 年金額:年間いくら受け取れるのか?
1年間に受け取れる年金の総額が記載されています。
この金額は、障害等級、加入している年金の種類(国民年金か厚生年金か)、子の加算(18歳未満の子がいる場合)などによって決定されます。
具体的な金額を確認し、今後の生活設計に役立てましょう。
4. 年金証書番号:今後の手続きに不可欠な番号
年金決定通知書と同時に発行される「年金証書」に記載されている10桁の番号です。
これはあなたの年金に割り当てられた固有の識別番号であり、今後、日本年金機構に問い合わせたり、年金の各種手続きを行う際に必ず必要となります。
大切に保管し、いつでも確認できるようにしておきましょう。
5. 次回診断書提出年月日:更新手続き時期の確認
多くの障害年金受給者は、障害の状態に変化が見込まれるため、1〜5年の期間を定めて支給が認められています。
この場合、定期的な更新手続きが必要です。
ご自身の更新時期は、年金証書に記載されている「次回診断書提出年月」で確認できます。
この年月が、更新手続きを行う時期となります。通常、更新月はご自身の誕生月となります。
提出期限である誕生月の月末を過ぎると、年金の支給が一時的に止まることがありますので、必ず確認しましょう。
不支給!?却下!?どうすればいい?

多くの時間と労力をかけてやっと申請ができたのに、「不支給決定通知」や「却下通知」が届いたら
それだけで心が折れてしまう人は多くいます。
また、それにより病状が悪化する人もいます。
このようなときこそ、冷静に今後どうするか考えていきましょう。
日本年金機構から届く不支給や却下の通知は、その詳細な理由が明記されていません。
専門用語や法律用語で記載されており、具体的にどういうことなのかわかりにくくなっています。
では、どうするか見ていきましょう。
不支給決定通知とは
「不支給決定通知」は、障害の程度が法律で定める程度の該当していない場合(障害基礎年金請求では2級以上。障害厚生年金では3級以上に該当していない場合)に送られてきます。
この通知が届いたら、不支給決定をやむを得ないものとして受け入れるのか、それとも決定を不服として審査請求をするのか、早急に決めなければなりません。
審査請求は、通知を受け取ってから3か月以内に行わなければなりませんが、なぜ不支給になったのか原因を確認し、その原因をつぶしたうえで請求しなければ、また「不支給決定」と同じことの繰り返しになってしまいます。
対策に係る時間を考慮すると、速やかな意思決定が必要となります。
却下通知とは
「却下通知」は、例えば「初診日が確定できない」「保険料納付要件が満たされていない」等、障害年金を請求する要件が整っていない場合に送付されてきます。
この場合も、審査請求は通知を受け取ってから3か月以内に行わなければなりませんので、「却下」を受け入れるか否か速やかに決める必要があります。
障害等級の決定に関する情報の入手
審査請求をする前に、まず「なぜこのような決定になったのか」を確認しましょう。
決定された障害等級(等級非該当による不支給を含む)に不服がある場合、「なぜそのような決定になったのか」を知る方法が2つあります。
ひとつは、年金事務所の窓口で決定内容(口頭説明)を受ける方法、もう一つは個人情報開示請求により障害状態の認定表(認定調書)の写しを入手する方法です。
個人情報開示請求は、厚生労働大臣(窓口は厚生労働省大臣官房総務課公文書監理・情報公開室)あてで行います。
手続きの方法や流れは下記のリンクをご参照ください。
裁定請求書のコピーは保管していますか
裁定請求時に年金機構へ書類を提出する前に、必ずコピーを取っておきましょう。
不支給決定や却下通知を受けてしまったときに、社会保険労務士等専門家に相談する場合や、自身で診断書がどの程度だったのか等後から確認する場合に、手元に何もなければ確認しようがありません。
当事務所でも、ご自身で申請したが不支給になったという相談者の方が来所されますが、申請書類のコピーを取っておられない方が多くいます。
再審査請求の対策を練るためにも、請求書類のコピーは重要な役割を果たします。
では、なければどうするか?
請求書類のコピーは年金事務所等に提出後でも郵送請求が可能です。
住所地を管轄している年金事務所(お客様相談室)に電話をして、「提出した請求書類一式のコピーを送って欲しい」旨と基礎年金番号、氏名、生年月日、住所を伝えると3週間前後でご自宅に郵送されます。
不服申立て手続きには3か月の期限があり、再請求は請求月の翌月からが支給対象となります。
手元に請求書類のコピーがあれば、時間の節約にもなります。
そのためにも申請書類を提出する前に請求書類一式のコピーを保管しておくことをお勧めします。
まとめ

障害年金の決定通知書は、今後の生活設計に欠かせない重要な書類です。
手元に届いたら、必ず内容を確認しましょう。
不明な点があれば日本年金機構に問い合わせるようにしましょう。
また、不支給決定や却下の決定がなされた時は、まずいったん冷静になり、今後の対策を考えましょう。
一人で抱え込まずに、お近くの年金事務所や社会保険労務士等に相談することをお勧めします。
シェアする