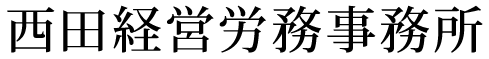障害年金の「初診日」 あなたの受給を決定づける最重要ポイント

この大切な制度を利用する上で、最も正確に把握し、証明する必要があるのが「初診日」です。
なぜ「初診日」がそこまで重要なのでしょうか?
障害年金は、あなたが病気やケガで初めて医師の診察を受けた日、つまり「初診日」に、どの公的年金制度(国民年金、厚生年金など)に加入していて、かつ、保険料の納付要件を満たしているかどうかが問われるからです。
この条件を満たしていなければ、残念ながら障害年金を受給することはできません。
すなわち「初診日」は、障害年金を請求する上での必須要件なのです。
初診日が確定しない限り、その先へは進めません。
目次
- ○ 障害年金における「初診日」
- ・「相当因果関係」とは
- ・「再発」または「継続」とは
- ・「社会的治癒」とは
- ○ 初診日の確定は難しい
- ・「発病日」とは
- ○ 初診日が分からない時は
- ・第三者証明に書くこと
- ○ まとめ
障害年金における「初診日」

一般的に認識されている「初診日」は、「その傷病ではじめて病院に行った日」でしょう。
しかし、障害年金の世界では、健康診断日が初診日になることがあったり、相当因果関係がある傷病の初診日が請求上の初診日であったりします。
つまり場合によっては一般的な認識の初診日と障害年金請求における初診日が違うことがあります。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、はじめて医師又は歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいい、具体的には次のように取り扱われています。
(1)初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
(2)同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
(3)過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
(4)傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
(5)じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
(6)障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
(7)先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
(8)先天性疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
(9)先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
障害年金申請のための3つの条件 初診日・保険料納付要件・障害の状態
「相当因果関係」とは
「前の疾病や負傷なければ、後の疾病は起こらなかっただろう」と認められる場合は、「相当因果関係あり」とみて、前後の傷病を同じ傷病として取扱います。
その場合は、前の疾病や負傷で最初に医師等の診療を受けた日が「初診日」となります。
具体的に例示されている相当因果関係は、次のとおりです。
〇相当因果関係あり
・糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
・糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎または慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの(両者の期間が長いものであっても)
・肝炎と肝硬変
・結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
・手術等の輸血により肝炎を併発した場合
・事故または脳血管疾患による精神疾患がある場合
・肺疾患に罹患し手術を受け、その後呼吸不全を生じたもの(両者の期間が長いものであっても)
・転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの
〇相当因果関係なし
・高血圧と脳出血・脳梗塞
・糖尿病と脳出血・脳梗塞
・近視と黄斑部変性・網膜剝離・視神経萎縮
「再発」または「継続」とは
過去の傷病が治癒し再度同じ傷病が発生した場合は、過去の傷病と再発した傷病は別の傷病とされます。ただし、治癒したと認められない場合は、その傷病が継続しているものとして取り扱われます。
なお、医学的には治癒していないとされる場合でも、障害年金の審査上「社会的治癒」が認められる場合は、過去の傷病と再発した傷病は別の傷病とされます。
「社会的治癒」とは
症状が安定して特段の療養がなく、長期的に自覚症状や多角症状に異常が見られず、普通に仕事や生活ができている期間がある場合に「社会的治癒」とされます。
「社会的治癒」の状態に該当するかどうかは、診断書や病歴・就労状況等申立書等の内容によって、「個別に」判断されます。
初診日の確定は難しい

上記で述べたように、初診日の確定は非常に難しいものです。
ご自身が「〇年○月〇日が初診日だ」と思っていても、これが正しいと短絡的に考えてはいけません。ここを誤ると、後に診断書を取得した時や審査請求上矛盾が起きてしまいます。
では、初診日がいつなのか精神障害の例で考えてみましょう。
精神疾患の場合、頭痛や腹痛などの身体症状でまず内科にかかることが多いものです。
この場合の初診日は、このような身体症状で「最初に内科等の診察を受けた日」となります。
・「うつ病ということですが、初診日はいつ頃ですか?」
「平成○年○月〇日です」
この例ではご本人が障害年金請求における初診日の考え方を知らない場合、まず体調の不調を感じて内科等を受診していても、内科等の診察を受けた日ではなく、精神科や心療内科を受診した日を答えているかもしれません。
・「うつ病ということですが、具合が悪くなり始めたのはいつ頃ですか」
「平成○年○月頃から、何となく頭が重くて。風邪でも引いたのかと思い、まずは近くの病院へ行きました。」
この例であれば、精神科や心療内科に行く前に受診した経緯を確認することができます。
通常、初診日の前には「発病日」があります。相当因果関係のある傷病の場合でも、必ず初診日より先に「具合が悪くなった日」があります。まずは「具合が悪くなりかけたのはいつ頃か」と考え始めると、現在の状態に至った経緯や病院の受診歴を整理して考えることができます。
また、どうしても自身で思い出すことができない、あるいは記憶が曖昧であるなどの場合は、主治医に確認し「初診日」の候補を探していきましょう。
「発病日」とは
「初診日」と関連の深い「発病日」についても確認しておきましょう。
傷病の発生時期は原則的に、「自覚的・他覚的に症状が認められた時」とされています。
ただし、先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても、通常の生活や仕事をしている場合は「症状が自覚された時」あるいは「検査で異常が発見された時」をもって発病日とされます。
具体的には、次のような場合です。
・医師の診療を受ける前に自覚症状が現れた場合は、その日
・自覚症状が現れずに医師の診療を受けた場合は、診療日
・慢性的疾患(糖尿病・腎不全等)のように傷病の病歴が引き続いている場合は、最も古い発病日
・過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合は、再発した日
・健康診断で異常が発見された場合は、異常の程度により健康診断日
・交通事故等の場合は、事故が発生した日
・じん肺(じん肺結核を含む)については、長期間鉱山等の業務に従事し、粉塵を吸入して発生する業務上の疾病であり、その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とされる(なお、確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書およびじん肺健康診断結果証明書の添付が必要)
・先天性疾患、網膜色素変性症当については、通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日
・先天性股関節脱臼については、完全脱臼した状態で生育した場合は厚生年金保険期間外発病とされるが、それ以外の者で青年期以降になって変性症股関節症が発症した場合は、症状が発生した日が発病日となる
初診日が分からない時は

初診の病院が分かっていれば、そこで初診の証明である「受診状況等証明書」の作成をお願いしましょう。
しかし、初診の病院での最後の診察から5年以上経過している場合は、カルテを廃棄されている可能性があります。
初診日がかなり前でカルテを廃棄されていたり、初診の病院が廃院している場合など、初診日の証明を出してもらえないこともあります。そのような場合は、次に受診した医療機関にお願いして、ダメな場合は3番目4番目とたどっていきます。
では、3番目の病院でカルテが残っていた場合を例にとると、まずそこで受診状況等証明書を書いていただきます。そして、初診の証明を書いてもらえなかった1,2番目すべての医療機関に関して「受診状況等証明書が添付できない申立書」に自分自身で記入し、申請書類とします。
その際に、受診状況など初診証明の手がかりとなる資料を添付します。
資料例として
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・身体障害者手帳等の申請時の診断書
・お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券
・小学校、中学校等の健康診断の記録や成績通知表
・健康診断の記録(勤務先に保存されている場合も)
・入院記録、入院計画書
・生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
などがあります。
健康診断を受けた日(健診日)は原則、初診日として取り扱いませんが、最初に受診した医療機関にカルテの保存が無い場合、医学的に治療が必要と認められる状態であれば、健診日を初診日とするよう申し立てることにより、健診日を初診日として申請することも可能です。
また、平成27年10月改正により、20歳以降に初診日がある障害年金についても、第三者(隣人、友人、学校の先生や上司、民生委員など)が証明する書類を添付することができるようになりました。(原則として、複数の第三者による証明が必要です。)改正前は20歳未満の取扱いに限定されていましたが、この第三者証明とともに本人申立の初診日について参考となる他の資料が併せて提出された場合には、審査の上、本人の申立た初診日が認められます。
第三者証明に書くこと
第三者証明は、誰に書いてもらってもよいというわけではありません。民法上の三親等内の親族による証明は認められません。(いとこは認められます)
次のような方が具体的な第三者(4親等以上の親族、隣人、友人、学校の先生や上司、民生委員など)といえます。
・直接的に初診日の頃の状況を見た人
・直接的には初診時の状況を見ていないけど、本人(請求者)やその家族から初診日の頃の状況を聞いた人
・直接的には初診時の状況を見ていないけど、障害年金を請求する5年以上前に、本人(請求者)やその家族から初診日の頃の状況を聞いた人
第三者証明に記入することは、次のようなものです。
①申立人の住所・氏名・連絡先・請求者との関係
②傷病名・医療機関・診療科・所在地・初診時期
③申立者が知っている申請者の当時の状況等
しかし、友人や学校の先生といえども、なかなか自身の傷病について話しすることは少ないかと思います。ましてや受診した病院や時期を知っていることを書くことは難しいでしょう。記入できない項は無理して記入する必要はないでしょう。重要なことは、傷病を発症した当時の状態を具体的に挙げ、現在の障害と関連があると思われる事実やエピソードなどです。
当事務所の事例でも、初診の病院でのカルテは廃棄されていましたが、当時診察された医師が覚えておられて第三者証明を書いてくださったことがありました。
また、幼少期に一緒に遊んだ友人がその当時の状況を覚えていて、第三者証明に協力いただいたケースもあります。
精神疾患の相談者様の場合では、初診の病院が廃院していましたが、職場の同僚や上司が発症時期の状態を覚えておられて、第三者証明を書いていただき、障害年金を受給することができました。
このように第三者証明は、初診日が分からない、証明書を書いてもらえない等の場合に、有効な手段といえるでしょう。
まとめ

今回は、障害年金申請における「初診日」の定義と具体的な立証方法に焦点を当てて解説いたしました。初診日は単なる日付ではなく、その後の年金受給資格を左右する極めて重要なファクターです。医療機関の協力が得られない場合や、古い記録の探索など、複雑なケースに直面することもあります。
当事務所では、そうした困難な初診日特定についてもサポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
シェアする