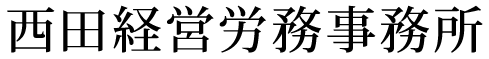遺族年金の見直しが決定しました

本改正のねらいは
①遺族厚生年金を、女性の就業率上昇等の社会変化に合わせ、男女問わず受給しやすくすること
②遺族基礎年金を、子ども自らの選択によらない事情にかかわらず、受給しやすくすること
の2点です。
年金制度は私たちの普段の生活に直接的に影響する重要な制度です。法改正によって自身の生活に影響はあるのか、ある場合はどう変わるのか、確認しておきましょう。
目次
- ○ 遺族厚生年金の見直し
- ○ 遺族基礎年金の見直し
- ○ 施行はいつから?
- ○ まとめ
遺族厚生年金の見直し
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた会社員や公務員が亡くなった場合に、その遺族が受け取れる年金です。今回の改正で大きな変更点があるのは、主にこの遺族厚生年金です。遺族厚生年金における支給要件や給付内容の改正は以下の通りです。
1. 支給期間が「原則5年」の「有期給付」へ
•これまで: 30歳以上の子のない妻は、原則として一生涯遺族厚生年金を受給できました。
•改正後: 20代〜50代の子のない配偶者(男女問わず)は、原則として5年間の有期給付となります。
・ただし、障害がある場合や、5年経過後も所得が低いなど、生活再建が難しいと判断される場合には、支給が継続される仕組みも検討されています。
•対象外となるケース
・すでに遺族厚生年金を受給している方
・60歳以上で受給している方
・18歳未満の子を養育している方(この場合は、子が18歳になる年度末まで遺族基礎年金・遺族厚生年金が現行通り支給されます)
2. 男女間の受給要件の差が解消される
•これまで: 子のない男性は、55歳以上でないと遺族厚生年金が受給できないなど、男女間で受給要件に差がありました。
•改正後: 20代〜50代の子のない配偶者であれば、男性も女性も等しく5年間の有期給付の対象となります。
3. 「有期給付加算」が創設され、年金額が増額
•支給期間が5年間に短くなる分、その期間中の年金額を増やす「有期給付加算」が新たに設けられます。これにより、当面の生活再建を支援する狙いがあります。
4. 「年収850万円」の収入要件が撤廃
•これまで: 遺族厚生年金を受給するには、遺族の年収が850万円未満(所得655万5,000円未満)という収入要件がありました。
•改正後: 20代〜50代の子のない配偶者については、この収入要件が撤廃される予定です。これにより、収入の多寡に関わらず、死別による影響を考慮して遺族厚生年金を受給できるようになります。
5. 「中高齢寡婦加算」は段階的に見直し・廃止
•40歳から65歳までの妻に支給されていた「中高齢寡婦加算」は、男女格差の解消という観点から、段階的に減額され、将来的には廃止される方向です。
6. 「死亡時分割」制度の導入
•亡くなった配偶者の年金記録(老齢厚生年金の記録)の一部を、残された配偶者の将来の老齢年金に上乗せする「死亡時分割」が導入される予定です。これにより、65歳以降の自身の老齢年金が増える可能性があります。
遺族基礎年金の見直し
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、18歳未満の子どもがいる配偶者、または18歳未満の子ども自身が受け取れる年金です。
今回の改正において遺族基礎年金については、主に「子の支給停止規定の見直し」がポイントとなり、直接的に大きな影響を与えるのは、主に以下の点です。
1.子に対する支給停止規定の見直し
現行制度では、親が再婚したり、高所得になったりした場合、子どもが受け取るべき遺族基礎年金が支給停止されるケースがありました。
今回の改正では、こうしたケースで、実態に応じて子どもが遺族基礎年金を受け取れるようになる見直しが行われます。例えば、母親が再婚し、新しい父親と一緒に暮らしている場合でも、子ども自身の生計が故人によって維持されていたと認められれば、子どもが遺族基礎年金を受け取れるようになる可能性があります。
2.支給停止であったが新たに支給となるケース
①配偶者が子の生計を維持し、死別後に再婚
②死亡者との生計維持関係の確認に用いる収入基準(850万円)を超える配偶者が子の生計を維持
③直系血族(又は直系姻族)の養子となる
④(生前に既に両親が離別しており、)子の生計を維持していた被保険者が死亡した後、元配偶者が子を引き取る
※上記の事例すべて、配偶者が遺族基礎年金を受けられないこと等により、子が遺族基礎年金を受給できる可能性があります。
施行はいつから?
実際の施行は2028年4月以降、段階的に行われる予定です。特に女性の有期給付への移行は、時間をかけて徐々に対象年齢が引き上げられる予定です。
まとめ

今回の見直しは、共働き世帯の増加や女性の社会進出といった社会の変化に対応し、「男女問わず、配偶者を失った場合の生活再建を支援する」という考え方が強くなっています。
特に、若い世代や子のいない配偶者にとっては、終身で年金を受け取るという前提から、一定期間で自立を促す制度へと変わるため、影響が大きいと言えます。ご自身の状況がどのように変化するか、事前に確認し、必要に応じてライフプランを見直すことが重要です。
シェアする