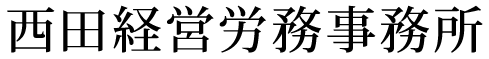自立とは「依存先を増やすこと」

一人で何でもできること?
誰にも頼らずに生きていくこと?
もしそう思うなら、少し立ち止まって考えてみませんか?
障害のある人もない人も、一人で生きることはできません。
今回は、「自立」と「依存」について新たな視点を与えてくれる、東京大学先端科学技術研究センター准教授の熊谷晋一郎先生の考え方を紹介したいと思います。
目次
- ○ 従来の「自立」の考え方
- ・「依存」の重要性
- ○ 「自立」とはどういうことか?
- ○ 依存先が少ないと
- ・職場の人間関係で考えてみると
- ○ 障害年金も依存先の一つです
- ○ まとめ
従来の「自立」の考え方

熊谷晋一郎先生は、小児科医であり、当事者研究の第一人者として知られています。ご自身も脳性麻痺の当事者であり、その経験から、障害や病気を持つ人の立場に立った研究や情報発信を積極的に行っています。
熊谷先生は、「自立」と「依存」について、従来の考え方とは異なる独自の視点を持っています。
従来の「自立」とは「誰にも頼らず一人で生きていくこと」と捉えられがちですが、熊谷先生はこの考え方は現実的ではなく、むしろ人を孤立させてしまうと指摘しています。
特に、障害や病気を持つ人にとって、完全に一人で生きることは困難です。従来の自立の考え方は、その人らしい生き方を制限してしまう可能性があると述べています。
「依存」の重要性
熊谷先生は「自立とは依存先を増やすこと」という考えを様々な分野で発信しています。ここでいう「依存」とは「誰かに頼る事」であり、決してネガティブな意味ではありません。
人は誰でも、何らかの形で他者や様々なものに依存しながら生きています。熊谷先生は、依存を『人が生きる上で必要な、他者や社会との相互関係』と捉えています。
例えば、私たちは食事をするために食材を育てた人、調理した人、販売した人など、多くの人に依存しています。「依存先を増やす」ということは、特定の誰かに依存するのではなく、様々な人やものに依存することで、より豊かな人間関係を築き、自立した生活を送ることができるという考え方です。
それが「自立とは、依存先を増やすこと」という言葉で表現されています。
「自立」とはどういうことか?
では、「自立」とはどういうものなのか。熊谷先生はご自身の体験から、次のように語られています。
『一般的に「自立」の反対語は「依存」だと勘違いされていますが、人間は物であったり人であったり、さまざまなものに依存しないと生きていけないんですよ。
東日本大震災のとき、私は職場である5階の研究室から逃げ遅れてしまいました。なぜかというと簡単で、エレベーターが止まってしまったからです。そのとき、逃げるということを可能にする“依存先”が、自分には少なかったことを知りました。エレベーターが止まっても、他の人は階段やはしごで逃げられます。5階から逃げるという行為に対して三つも依存先があります。ところが私にはエレベーターしかなかった。
これが障害の本質だと思うんです。つまり、“障害者”というのは、「依存先が限られてしまっている人たち」のこと。健常者は何にも頼らずに自立していて、障害者はいろいろなものに頼らないと生きていけない人だと勘違いされている。
けれども真実は逆で、健常者はさまざまなものに依存できていて、障害者は限られたものにしか依存できていない。依存先を増やして、一つひとつへの依存度を浅くすると、何にも依存してないかのように錯覚できます。“健常者である”というのはまさにそういうことなのです。世の中のほとんどのものが健常者向けにデザインされていて、その便利さに依存していることを忘れているわけです。
実は膨大なものに依存しているのに、「私は何にも依存していない」と感じられる状態こそが、“自立”といわれる状態なのだろうと思います。だから、自立を目指すなら、むしろ依存先を増やさないといけない。障害者の多くは親か施設しか頼るものがなく、依存先が集中している状態です。だから、障害者の自立生活運動は「依存先を親や施設以外に広げる運動」だと言い換えることができると思います。今にして思えば、私の一人暮らし体験は、親からの自立ではなくて、親以外に依存先を開拓するためでしたね。』
出典 東京都人権啓発センター
依存先が少ないと
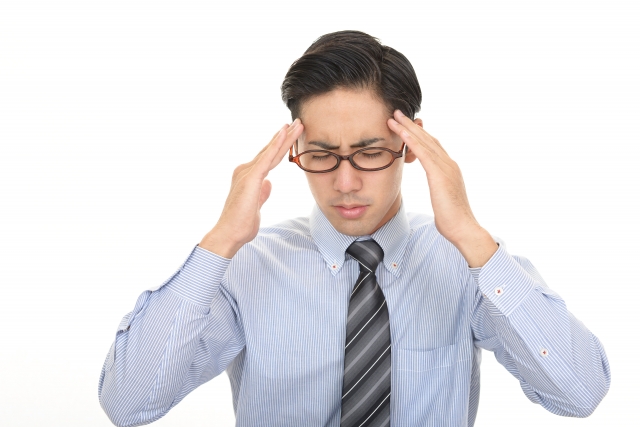
では、依存先が少ないとどうなるのでしょうか。依存先が少ないと、その依存先からの影響が大きくなり、結果として支配されるようになる可能性があります。
あるいは現状に不満があっても、他に頼る場所が少ないため、抜け出すことが困難になります。
また、一つの依存先に過度に依存すると関係が悪化した場合、精神的な支えを失い、大きなダメージを受ける可能性もあります。
これは障害のある方に限った話ではなく、育児や介護、友人関係や職場の人間関係で悩んでいる方など誰にでも当てはまることです。
職場の人間関係で考えてみると
例えば、職場の人間関係で悩んでいる人は、依存先が少ないとどのような弊害が生じるのでしょうか。
・精神的な孤立とストレスの増大
特定の同僚や上司との関係が悪化した場合、頼れる人がいなくなったり、精神的に孤立しやすくなります。また、悩みを相談できる人がいないことで、ストレスが蓄積し、心身の健康を害する可能性があります。
・仕事へのモチベーション低下
職場で孤立すると、仕事へのモチベーションが低下し、パフォーマンスにも悪影響が出る可能性があります。職場に行くことが苦痛になり、最悪の場合、退職につながることも考えられます。
・客観的な視点の欠如
特定の人物との関係に依存していると、客観的な視点を失い、状況を正しく判断できなくなることがあります。これにより、問題解決がさらに困難になり、さらなるトラブルを引き起こす可能性があります。
熊谷先生の「自立とは依存先を増やすこと」の考え方を取り入れることで、状況を改善できる可能性があります。
例えば、同僚だけでなく、他部署の人や友人、家族など、様々な人と交流することで、相談相手や助けを得られる可能性が広がります。
また、カウンセラーやキャリアコンサルタントなど、専門家に相談することで、客観的な視点からアドバイスをもらえます。
そして、仕事以外の趣味や自己啓発に時間を使うことも、「依存先を増やす」ことにもつながります。
障害年金も依存先の一つです

障害年金は、障害によって生じた経済的な困窮を助ける「依存先」を、社会全体で支え合う仕組みです。
通常の生活を送ることが困難になった場合、人は様々なものに依存せざるを得ません。家族、友人、福祉サービス、そして経済的な支援など依存先を増やすことで、人は生活を維持し自立へと向かうことができます。
障害年金は、そうした依存先の一つとして、経済的な基盤を支える役割を担います。これにより、障害者は経済的な不安を軽減し、他の依存先と連携しながら、より自立した生活を送ることが可能になります。
障害年金は、「依存」を否定するものではなく、依存先を多様化し、生活の安定と自立を支援する制度なのです。
障害年金申請のための3つの条件 初診日・保険料納付要件・障害の状態
まとめ

依存先を増やすことは、決して「誰かに頼りっぱなしになる」ということではありません。
様々な人や物や物事とのつながりを持つことで、自分らしい生き方を実現し、困難な状況を乗り越える力を得ることができます。
「依存」に対しての考え方は、時代と共に変化しています。
依存という言葉をネガティブにとらえるのではなく、その多面性を理解し、より豊かな生活を築くために役立てることが重要です。
シェアする