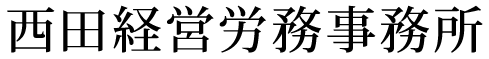ご存じですか?障害者手帳のメリットとデメリット
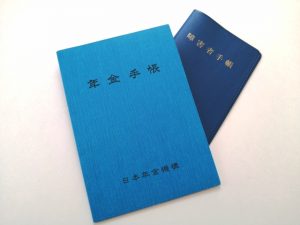
障害者手帳は、障害がある人が取得できる
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」
の3種類の手帳を総称した一般的な呼び方です。
いずれの手帳を取得している場合でも、障害者総合支援法の対象となり
様々な支援策が講じられています。
障害者手帳を取得することは任意ですが、
自治体や事業者などの様々なサービスが受けられ、経済的な負担の軽減、
社会参加の機会が広がるなどのメリットがあります。
目次
料金の割引や助成を受けることができる
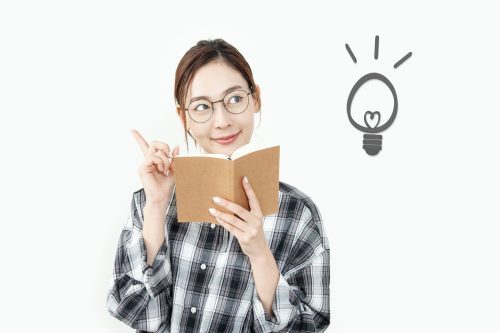
自治体や事業者によって内容が異なりますが、様々な料金割引や助成制度があります。
①医療費の助成
自立支援医療(精神科の診療費が1割負担になる制度)は手帳が無くても適用されます。
自治体によっては精神障害者手帳を保持している方にはさらに「心身障害者医療費助成制度」等の名称で
医療費を助成する制度があります。
②公共料金(NHK受信料・上下水道料金・公共交通機関の運賃など)や携帯電話料金などの割引
③身体障害者手帳の場合、補装具に係る費用の助成
他にも映画館、美術館、博物館やテーマパークの入場料(一部)の障害者割引などがあります。
障害者手帳の種類、障害等級によっても内容が異なる場合があるので、手帳交付時に配布されるガイドブック
お住いの市区町村のウエブサイト、市区町村の障害者窓口等でご確認ください。
税金が優遇される
所得税や住民税、相続税などの優遇措置があります。
これらは国税なので、どの障害者手帳にも共通するメリットです。
①所得税の控除(特別障害者控除)
・身体障害者手帳の1級・2級、精神障害者福祉手帳1級、重度知的障害者(療育手帳A)の方
所得控除40万円
・身体障害者手帳3級から6級、精神障害者福祉手帳2級・3級、中度・軽度知的障害者(療育手帳B1・B2)の方
所得控除27万円
②住民税の控除
・特別障害者控除 所得控除30万円
・それ以外の障害者控除 所得控除26万円
③相続税の障害者控除
障害者が相続(遺贈を含む)で財産を受け継いだ場合、その人の相続税の金額から一定額を減らすことができます。
・一般障害者の場合
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
・特別障害者の場合
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
④贈与税が非課税になる
特別障害者(※)への贈与については最大6,000万円、その他の特定障害者については最大3,000万円まで非課税になります。
※特定障害者とは、特別障害者や精神障害者のことをいいます。
⑤利子・預貯金の利息が非課税になる
銀行などの預貯金、貸付信託、公社債など350万円まで非課税の適用を受けることができます。
また、自動車税・軽自動車税も割引や免除となる場合があります。
これらは地方税なので、各都道府県や市区町村が独自に実施しています。
詳しくはお住いの自治体窓口にお問い合わせください。
「障害者雇用枠」へ応募できる

障害者手帳保持者は、障害のある人の特別な雇用枠である「障害者雇用枠」へ応募することができます。
障害者雇用では、障害の状況、症状、体調への配慮を受けながら働くことができます。
さらに就職にあたって利用できる支援制度の幅も広がり、働き方の選択肢も広がります。
障害者手帳を持つデメリットは?
障害者手帳を取得することで、障害を知られてしまうかもという心配があるかもしれません。
しかし、自分から伝えない限り持っていることはわかりません。
また、取得したことを職場などに伝える必要もありません。
そうであればデメリットは特にないように感じますが、やはり心理的な負担はあるかと思います。
障害手帳を取得せず生活することに越したことはありません。
しかし手帳を持つことで、障害による負担や不便を軽減できるかもしれません。
また、障害者手帳は、必要がなくなれば返納することもできます。
心身機能が改善したり、仕事や生活において「障害」を感じることがなくなれば
手帳を持たないことを選ぶこともできます。
手帳を持つことに心理的負担を感じるのであれば、無理に取得することはありません。
障害年金や障害者手当、自立支援医療など手帳を取得せずとも利用できる制度もあります。
自分はどのように生活していきたいのか、医師や家族等と相談の上、選択しましょう。
関連リンクはこちら
まとめ

障害者手帳を取得することで、様々なサービスや助成、税金の優遇措置などを受けることができます。
経済的な自立や、就労の選択肢の幅も広がります。
ご自身にとっての必要性などよく考えていただき、障害者手帳を利用することを検討してみてください。
簡単なご質問はLINEからお気軽にどうぞ。
LINEアカウント名のみは当事務所に通知されますが、
それ以外の個人情報の提供は一切必要ありませんのでご安心ください。
下のバナーより友達追加していただき、トーク画面にて質問を送信してください。
![]()
シェアする